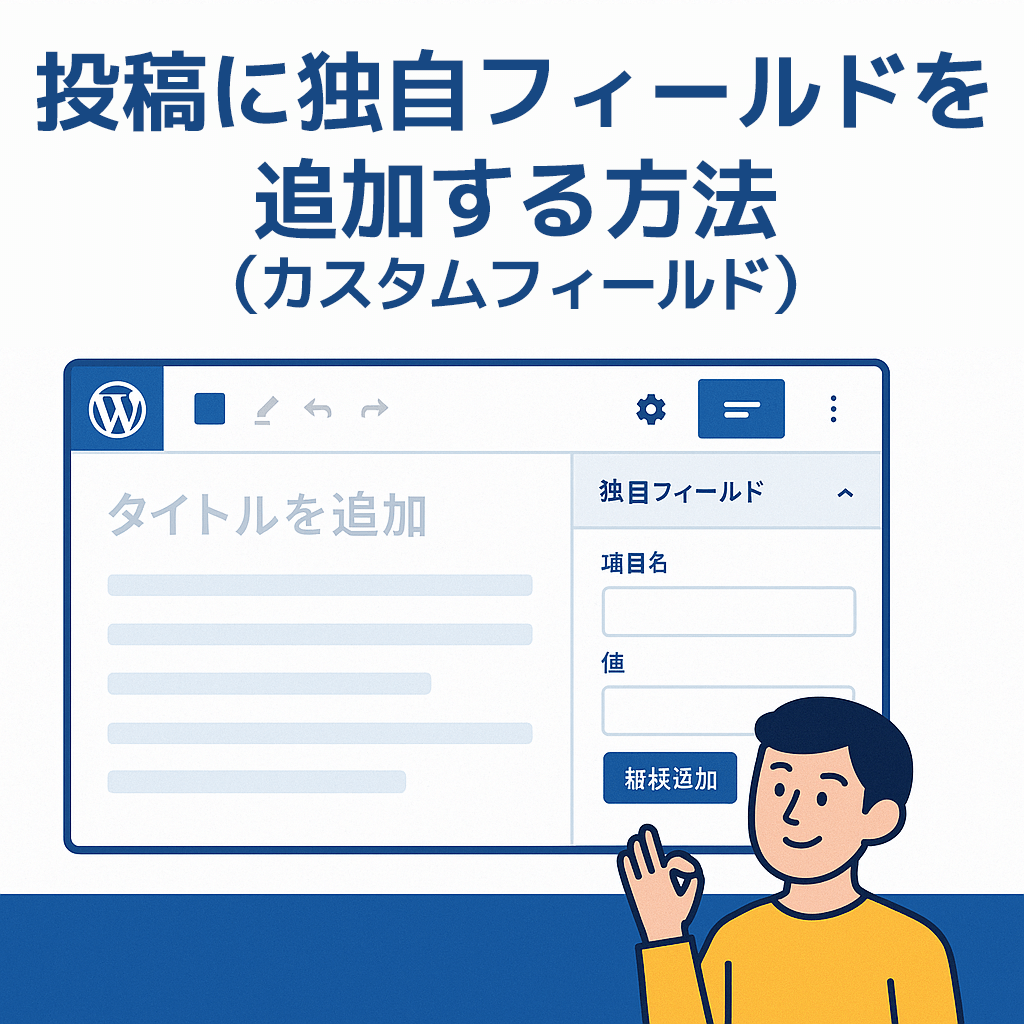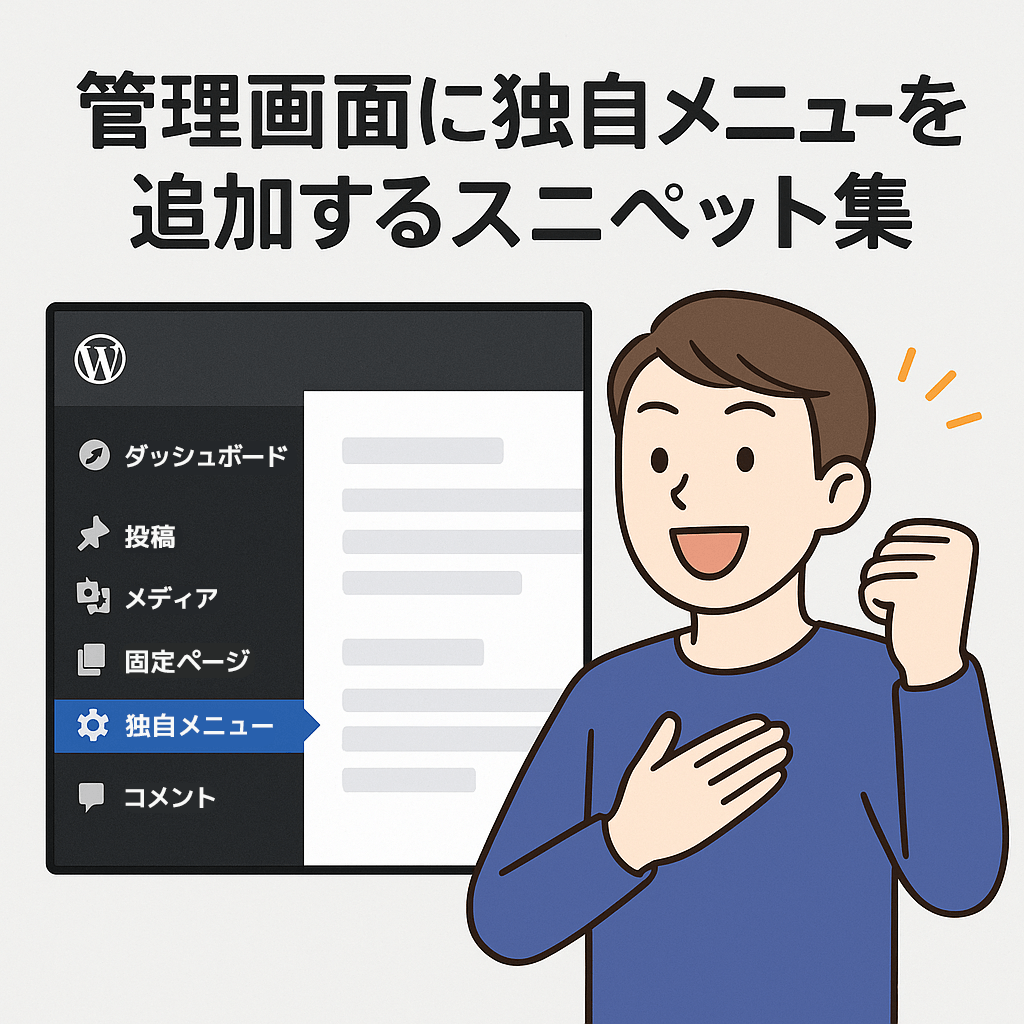WordPressでカスタム投稿タイプを追加する方法
- ブログ以外に「事例」「お客様の声」「製品」などを整理して掲載したい(CPTで情報設計をしたい)
- プラグイン任せではなく、将来の拡張・リライトやSEOまで見据えて設計したい
- パーマリンク(スラッグ)やアーカイブ構造、タクソノミー連携で迷った経験がある
WordPressレベル別 対応難易度
赤:外注推奨 オレンジ:条件付き自力可 緑:自力対応可
カスタム投稿タイプ追加の全体像と対応方針
「記事」以外の情報(製品・事例・FAQなど)を整理して見せたいときに、カスタム投稿タイプ(CPT)は強力です。
テーマ functions.php での実装が基本ですが、運用やSEOを踏まえた設計が肝心となってきます。
目的→情報設計→スラッグ/パーマリンク→権限と編集フロー→テンプレート連携という順で進めると安全です。
WordPressでカスタム投稿タイプを追加する方法 ~レベルごとのおすすめ対応
「何を増やすか」を決める
赤レベルの方は、実装そのものより“要件の言語化”に注力していきましょう。まずは「何を載せる?(例:製品、導入事例、FAQ、スタッフ紹介)」「誰が編集する?」「どのページから見せたい?」を固めます。
ここで迷うと、作ったあとに運用が回らず、放置→サイトが散らかる…のコンボになってしまいます。
要件整理のコツは、
①一覧で比較される情報項目(価格・カテゴリ・タグ・特徴)
②詳細ページで深掘りする項目(本文・画像・仕様表・よくある質問)
③サイト全体の導線(トップ・サービス・ブログからのリンク)
これらを先に考えること。
ここが固まれば、スラッグ(/products/ など)やパーマリンク(/products/sku-123/ など)もブレません。
また、「固定ページで代用できないか?」の逆張り確認も重要です。規模が小さく「5件だけ、更新は年1回程度」なら固定ページ+手作業の方が早いケースもあります。カスタム投稿タイプは便利ですが、メンテナンス(テンプレート、表示調整、検索/絞り込み)を伴うため、必要性が薄いなら導入しない判断も正解です。
結論:要件整理=あなた、実装=外注が最短で安全です。外注時は「スラッグ/パーマリンク規則」「アーカイブ有無」「サイドバー/パンくず/サイト内検索に含めるか」「今後の拡張予定」を必ず共有しましょう。
設計→実装→表示確認をスモールスタート
オレンジレベルの方は、“設計ファースト”→“最小実装”→“段階的に拡張”の流れで行います。いきなり複雑にせず、まずは下記を小さく決めます。
- スラッグ:例)/case/(日本語は避ける。英小文字・ハイフンで短く)
- パーマリンク:例)/case/%postname%/(将来の移設にも強い構成に)
- アーカイブの有無:一覧を持つか?トップやメニューからどう繋ぐか?
- タクソノミー:カテゴリ/タグを持たせるか?既存カテゴリと混ぜないか?
- 検索・絞り込み:将来 Facet/条件検索を想定するなら、項目名を先に決める
テンプレート側は、アーカイブ(archive-{post_type}.php)とシングル(single-{post_type}.php)を最低限用意します。テーマの部品(パンくず、カードUI、ページネーション)と整合を取っておくと、デザインの“浮き”が起きにくいです。
編集体験(Gutenberg)を高めるなら、カスタムフィールド(ACF等)やブロックパターンを併用して「入力フォームをわかりやすく」するのがコツです。必須/任意の整理・説明(ヘルプテキスト)・バリデーションでミスを減らし、画像サイズの運用ルールも決めておきましょう。
注意点として、リライトルール(パーマリンク構造)を変えると404やリダイレクトの連鎖が起きます。移行時は既存URLの洗い出し→301設計→テスト→反映の順に行いましょう。サイトマップ/検索コンソール更新、内部リンクの見直しも忘れずに行います。
最後に、権限(Capabilities)とロールです。投稿者が複数いるなら、「公開までは編集者が承認」「画像登録はメディア管理者のみ」など、運用フローを先に決めると事故が激減します。カスタム投稿タイプは「作る」より「回す」準備が9割です。
実装~運用最適化:拡張・SEO・パフォーマンスまで
緑レベルの方は、設計の正規化と長期運用の最適化が中心となる取り組みです。CPTの登録では supports・show_in_rest・menu_position・map_meta_cap・capability_type を要件に沿って最小/明示設定。ラベル(labels)は日本語UIの読みやすさに直結するため丁寧に。
テンプレート分離(パーツ化)とクエリの健全性(pre_get_posts・WP_Queryの条件最適化)で、アーカイブの表示速度と可読性を担保。カスタムタクソノミーの設計時は、UI/UX上の「分類の粒度」を揃え、重複軸や過剰なタグ化を避けます。
SEOでは、アーカイブのインデックス方針(noindex含む)と、構造化データ(FAQ/製品/レビューなど)をCPT粒度で定義。パンくず・サイト内検索・関連記事がCPTを横断できるよう、メタ/タクソノミー設計を先に決めます。画像最適化とリスト/詳細のスニペット整形はクリック率に直結。
編集体験は、ブロックテンプレート・テンプレートパーツ・パターンで“誰でも崩れない”状態に。ACF/Block Variationsでの入力制御、メディア規格のプリセット、レビュー/FAQなどの反復ブロックを「誤操作できないUI」に落とし込むと、運用コストが大幅に下がります。
移行・改修時は、WP-CLIでの一括操作、ステージング環境→差分デプロイ、301/正規化URLの網羅、検索コンソールのURL検査まで見届けること。最終的には、「入力→公開→効果測定→リライト」のサイクルを設計に織り込み、KPI(流入・CV・内部回遊)で継続改善しましょう。
カスタム投稿タイプを外注する場合のポイント
要件が固まっていれば、CPTの導入はスムーズです。費用や流れ、準備物の目安を掴んでおきましょう。
| 項目 | ポイント |
|---|---|
| 費用の目安 |
・CPT1種+一覧/詳細テンプレート+軽微なカスタムフィールドで 50,000~120,000円 ・条件検索・絞り込みや複合タクソノミー、構造化データ設計込みで 120,000~300,000円 ・大規模移行(既存記事の移設、301設計、検索最適化)は別途見積。緊急対応は割増になることも |
| 依頼の流れ |
1. 掲載目的・スラッグ候補・必要項目(一覧/詳細)を共有 2. ワイヤー/要件確定→見積→着手 3. ステージングで確認→修正→本番反映(公開後1~2週間の微調整期間を設けると安心) |
| 準備しておくと便利 |
・想定URL(アーカイブ/詳細)とナビゲーション位置(グロナビ/フッター) ・一覧カードの項目(サムネ/価格/タグなど)と優先順位 ・入力ルール(必須項目・画像サイズ・表記ゆれ基準)と運用フロー(下書き→承認→公開) |
カスタム投稿タイプは「作る技術」より「運用設計」で成果が決まります。目的→情報設計→スラッグ/パーマリンク→権限→テンプレ連携の順で、無理のない導線を整えるのが近道です。
赤は要件を固めて外注、オレンジは小さく作って検証、緑は拡張・SEO・運用最適化まで見届けるのがベストプラクティスです。
迷ったら「固定ページで代用できないか?」も常に検討を。将来の移設やURL設計まで視野に入れると、長期的なコストが下がります。
要件が揃っていれば、実装は意外と早いもの。まずはサイトの目的に合う構造を一緒に詰めていきましょう。