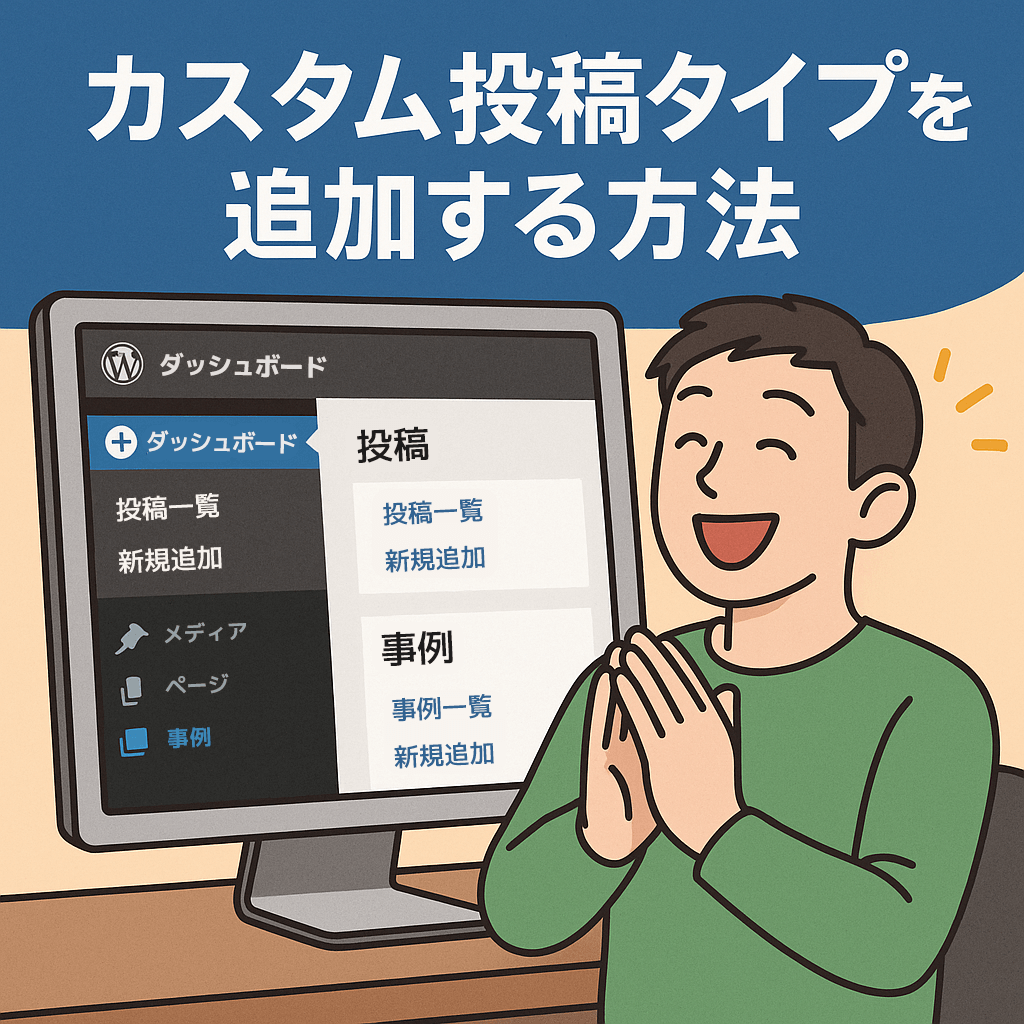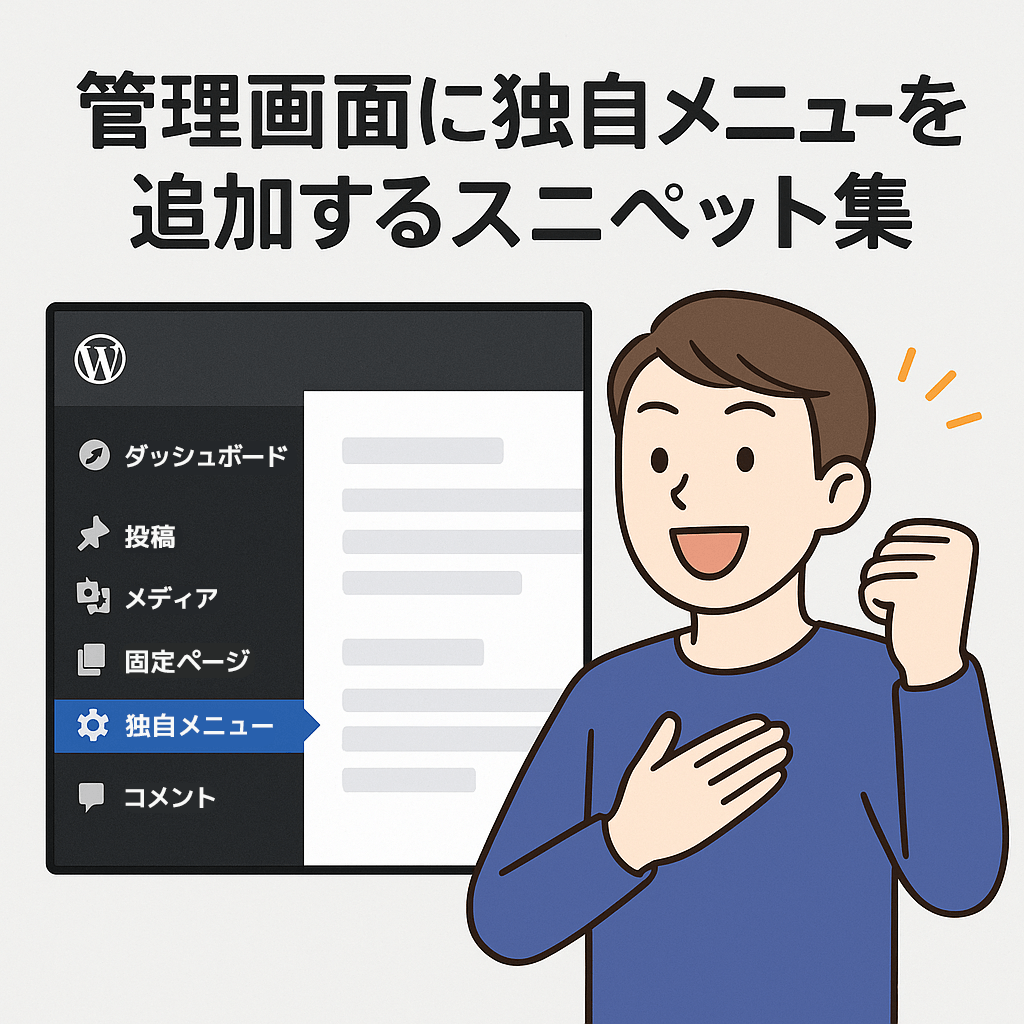投稿に独自フィールド(カスタムフィールド)を追加する方法
- 投稿に価格・担当者・開催日などの「項目」を足して、記事内や一覧で使い回したい
- カスタムフィールド(Advanced Custom Fields/ACF など)の使いどころを整理したい
- 将来の外注や運用体制を見据えて、“入れる場所と出す場所”の設計を失敗したくない
WordPressレベル別 対応難易度
赤:外注推奨 オレンジ:条件付き自力可 緑:自力対応可
投稿に独自フィールドを追加する全体像と対応方針
「投稿の本文とは別管理の項目欄を作り、テンプレートで整えて表示する」これがカスタムフィールドの本質です。
まずは“何を入力して誰がどこで使うか”を決め、次に入力UI(標準機能/プラグイン)→出力設計(テーマ/ブロック/ウィジェット/一覧)→運用ルール(必須/書式/責任者)を順に固めます。
『最初に項目を盛りすぎない』『命名と単位を統一する』『将来の再利用先を想定する』この3点が、長期運用で効きます。
カスタムフィールド実装 ~WordPressレベルごとのおすすめ対応
入力欄を増やす意味を理解しよう
「カスタムフィールド=魔法の追加ボタン」ではありません。目的は、主に再利用と表記ゆれ防止です。価格・日付・担当・会場・外部URLなどを本文から分離して、一覧カードや構造化データ、検索フィルター、CTA等に、同じ値を使い回せるようにできます。
赤レベルの方は、「どんな項目が必要か」だけ言語化しておけばOKです。あとから増やすことはできますが、命名や単位(円/税込、日時/タイムゾーン)を途中で変えるとデータが混ざる可能性があります。
業者に頼むときは、“表示サンプル”のワイヤー画像(カードや詳細ページ)を一緒に渡すとスムーズです。
やりがちな失敗は、「本文に毎回手書き」「表をコピペ」「記事ごとに表記がバラバラ」など。検索や並び替え、一覧表示の自動化が効かなくなり、のちの運用コストが跳ねます。最初は無理せず外注することをおすすめします。要件整理に集中しましょう。
標準機能 or プラグインの“判断ポイント”を押さえる
WordPressはデフォルトでも「カスタムフィールド」入力ができます。とはいえ、そのまま使うにも入力UIが素朴で運用ガイドが必要です。入力漏れや表記ゆれを最小化したいなら、フィールドタイプを揃えられるプラグイン(例:選択肢、日付、URL)のほうが楽なこともあります。
選定の判断軸は次のとおり。
- 入力の強制力:必須/書式/最小最大/プレースホルダー/説明文の有無。将来の引き継ぎを考えると重要です。
- 表示の柔軟性:テーマ側で値を呼び出してカードや表に配置しやすいか。ブロックエディタとの親和性は要確認です。
- 検索・絞り込み:カテゴリやタグでは足りない条件検索を将来やるか(例:料金帯/開催エリア/仕様)。
- メンテ性:日本語情報/ユーザー数/更新頻度/将来の乗り換え手順が整っているか。
設計時のコツは、「1項目=1用途」を徹底することです。
例えば、「価格(税抜)」と「価格(税込)」を別々に持つと二重管理になります。どちらか一方だけ保存し、表示時に表記を統一するルールを先に決めましょう。
日付と時間は同一タイムゾーンで、“表示フォーマット”と“保存フォーマット”を分けると迷子になりません。
自力でやる範囲は、入力欄の追加と、既存テーマの“差し替え不要な場所”への表示までに留めるのが安全です。テンプレート改変やアーカイブ一覧の並び替えなどに踏み込むと、構造把握が必要になりがちです。困ったら無理せず一旦止まり、外注に設計レビューを依頼することを検討しましょう。
“入力→格納→出力→再利用”を通しで設計
緑レベルの方は、スキーマ設計と運用フローまで踏み込みます。
具体的には、
- 入力:フィールドグループの粒度設計(投稿タイプ別/カテゴリ別/ロール別に表示)、必須・バリデーション・ヘルプ文の整備。
- 格納:メタキーの命名規則(接頭辞/スネークケース/単位を含めない)、将来の移行(CSV/JSON/エクスポート)方針。
- 出力:アーカイブ・カード・詳細・パンくず直下の「概要ボックス」・サイドバーの「ミニ情報枠」・構造化データ(イベント/製品/FAQ)。
- 再利用:検索の絞り込み、関連投稿のロジック、REST APIでのヘッドレス配信、LPの差し替え、サイト内比較表の自動生成。
詰まりやすいのは、“入力はあるのに出力先のUIが未設計”なケース。カードの横幅・改行・省略ルール、スマホ時の折返し、未入力時の表示(非表示/ダミー文/?)まで決めてから実装に入ると手戻りが激減します。
また、一覧並び替え・絞り込みは要件の変化に弱い領域。クエリ負荷・キャッシュ・検索導線を見越し、運用ボリューム(件数/同時更新数)まで想定しておくと、あとで“速くて壊れにくい”サイトになります。必要に応じて、非正規化やメタクエリ回避、検索専用のインデックス構築を検討しましょう。
最後に、チーム運用の作法。命名規則、必須/任意、単位、入力例スクショを1枚にまとめ、オンボーディングに組み込むだけで品質は段違いです。棚卸しは四半期に1回、使われない項目は潔くアーカイブへ。
カスタムフィールド改修を外注する場合のポイント
要件を固めて短期で仕上げたいなら、実装はプロに任せるのも手です。費用・流れ・準備物を把握しておきましょう。
| 項目 | ポイント |
|---|---|
| 費用の目安 |
・入力欄の追加と単純表示:20,000~50,000円(項目数/画面数で変動) ・一覧カード/検索/並び替え対応:60,000~150,000円 ・構造化データ/REST/API連携まで:120,000円~ |
| 依頼の流れ |
1. 目的と再利用先(どの画面で使うか)を箇条書き 2. 必要項目リスト(名前/型/例/必須/単位)を確定 3. ワイヤー(カード/詳細/検索UI)と運用ルールを共有 4. 見積→実装→試験→微調整→引き継ぎ資料 |
| 準備しておくと便利 |
・“表示サンプル”のスクショ(PC/スマホ) ・項目定義書(キー名/日本語名/型/必須/説明/想定値) ・既存テーマの制約(カード幅/列数/抜粋の長さ) ・将来したいこと(検索/比較表/構造化データ/多言語) |
カスタムフィールドは「本文を分解して、機械が扱いやすい形にする」ための仕組みです。入力設計と出力設計が噛み合った瞬間、一覧カード・検索・構造化データ・LP量産などまで、一気に効率的になります。
赤は要件整理に集中して外注、オレンジは標準機能/プラグイン選定まで、緑はスキーマと運用まで通しで設計が基本方針です。
“入れる→出す→再利用する”の回路を先に描けば、将来の拡張や担当交代にも強いサイトになります。迷ったら、設計レビューだけでもプロに頼むことをおすすめします。